 |
入園・入学前に育てておきたい力 ─ 幼児期に学力の土台を ─ |
 |
|||||||||||||
| 学校のねらい ─ すべての子供たちに確かな学力と豊かな人間性を身に付ける ─ | |||||||||||||||
| 1、言葉かけを大切にし、聞く力を! | |||||||||||||||
| ● ほとんどが一斉授業で学習が進むので、先生や友達の話をしっかり聞き取る力が必要です。 普段から子供の質問に対しては、誠実に答えてやると、頭の中で言葉を使って、言葉で考え、言語能力 の高い子になります。 言葉抜きに知的な発達は難しい。 濃厚な親子の対話を通して、新しい言葉や言い回しを会得し、聞く力も育ってきます。 親子でいっぱい話を交わすと、知識も言葉も豊かな子になっていきます。 ● 親に深く愛してもらった子は、言語能力をはじめとして運動能力、社会的能力、人格すべてにわたって、 その基礎がしっかり培われていきます。 |
|||||||||||||||
| 2、読み書きに関心を! | |||||||||||||||
| ● 今の小学1年生は、たった2カ月で、ひらがなの読み書きをすべて教わるようになっています。 教師用指導書には、わずか24時間で教え込むよう指示されています。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 学校により進度が変わる場合があります。 | |||||||||||||||
| かたかな・漢字 ─ 後期(2学期) | |||||||||||||||
| ● 速いスピードで学習していくので、入学前にあわてて教え込まれた子の中には、字の形も筆順もひどく でたらめなまま固着してしまう子がいます。 入学前にかなり読み書きができていないととてもついていけないというのが、今日の実情です。 書けないまでも読めるにこしたことはなく少なくとも自分と家族の名前はひらがなで書けるよう 教えてあげて下さい。 ● 読み書き計算の勉強の基礎が着実になされていた子は、勉強についていけます。 ● 文字を覚えるときには、遊びのようなおもしろさが必要です。 道や家でいっぱい見かける文字を意識させていくことが大切です。 ● 読み書き・文字に関心をもたせる。 学力の高い子は総じて本好きです。小さい時から文字を知り文章が読め、一人で本が読めるように なっていた子は、成績がよい。 幼児期に文字を覚えたり、本を読んだりする習慣のなかった子は、勉強の苦手な子になりがちです。 |
|||||||||||||||
| 3、生活の中で「数」の能力を! | |||||||||||||||
| ● 1~10まで数えられればよい。 特に、5までの数の合成(たしざん)・分解(ひきざん) 5は3と2 4と1 などの習熟は算数の学力の 最も基礎になるものです。 できれば10までの合成と分解が瞬時にわかるようにしてあげたいものです。 (10は0と10 1と9 8と2 ~ 10と0 9と1 2と8~) 0+10=10 1+9=10 2+8=10 3+7=10 ~ 10+0=10 9+1=10 8+2=10 7+3=10~ 10-0=10 10-1=9 10-2=8 10-3=7 10-4=6 10-5=5 10-6=4 10-7=3 10-8=2~ 大事なことは、毎日の生活の中で具体物を使って自然に楽しく練習することです。(コインとかおはじき等) |
|||||||||||||||
| 4、学力の土台は言語能力です。 幼児期からの読み聞かせで本好きな子に! | |||||||||||||||
| ● 学力の高い子は、語彙も多く知識も豊かです。 勉強は、本を読み、文字や文章を書くことが基本と なります。 読む力と書く力さらに「かず」の計算力を含め学力の基礎となります。 ● 絵本や物語の読み聞かせは、本好きにする出発点です。 絵本を聞き説明をしたり、絵物語を読んでやりながら疑問に思ったことや強い印象にを受けたことに ついて語り合う。言葉をもとに場の情景やイメージを頭の中に思い浮かべる力も発達していきます。 読み聞かせから、できるだけ早い時期(5歳より4歳/4歳より3歳/~)一人読み出来るようにように なった子は学力の高い子に成長していきます。 ● 読み聞かせをあまりしてもらえなかった子は、文章を読んでもその場面を臨場感をもって思い描くこと ができなく算数の文章題や国語、社会などの中身を読み取る力がいまひとつ伸びない。 ● 幼児期から文字に関心を持ち、読めるように教えていくと、語彙も多く知識も豊かになり、学力の土台 が築けます。 |
|||||||||||||||
| 5、発達の臨界期を考えて! | |||||||||||||||
| ● 子供の能力を発達させていくうえで、ある年齢までに指導しないと効果が上がらないという時期。 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| といわれています。 | |||||||||||||||
| 子どもが文字を知りたがる時期に教える。知らない文字や読めない文字を見つけたら、どんどん質問する 時期にめんどうがらずに教える。 |
|||||||||||||||
| 6、身につけておきたい生活習慣 | |||||||||||||||
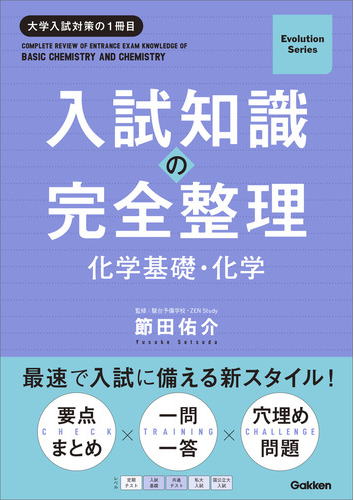 学研 入学のてびきより |
|||||||||||||||
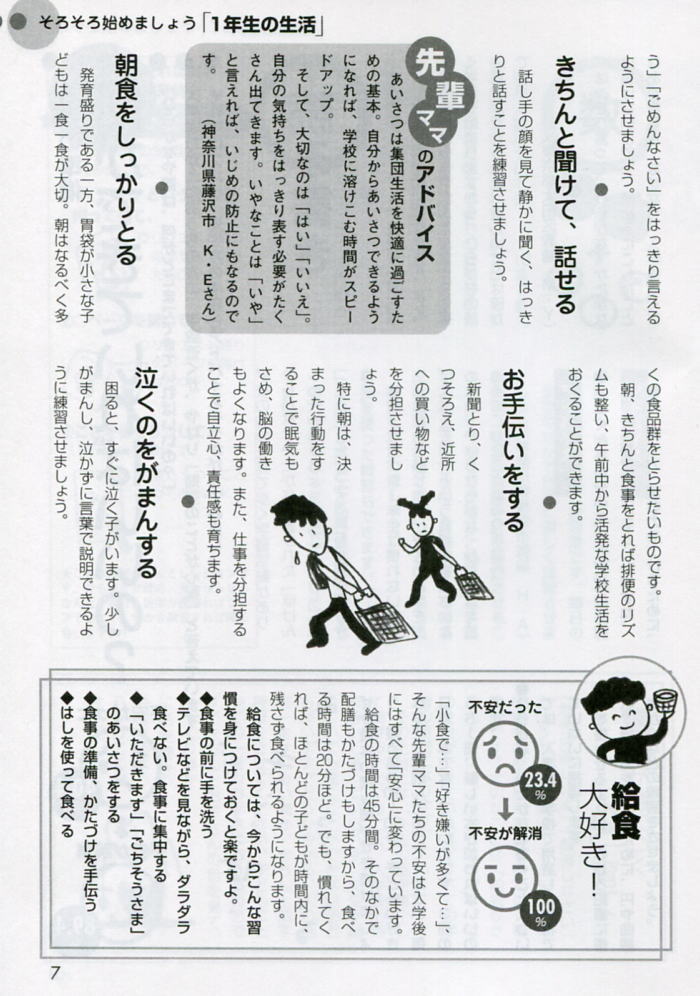 学研 入学のてびきより |
|||||||||||||||
| 7、入学前の5つの課題 | |||||||||||||||
| (1) 正しい姿勢で座る | |||||||||||||||
| ● 一定時間、机に座る習慣を!文字を書き続けていくには、正しい姿勢をとり続けることが必要です。 入学までにいつも正しい姿勢がごく自然にとれるようになった子は、じっくりとした落ち着きと集中力の ある子に成長します。 |
|||||||||||||||
| (2)鉛筆を正しく持たせる | |||||||||||||||
| ● 三角にぎりとか、とんがり持ちといった持ち方は勉強を長く続けられません。 力のない幼い子はそれだけで疲れてしまいます。 正しい持ち方をすると、鉛筆と人差し指がぴったりと寄り添っていて隙間がありません。 |
|||||||||||||||
| (3) 上下左右の識別のできるよう指導する。 | |||||||||||||||
| ● 左右が間違いなく分るということは、字を書く上で、とても大切なことです。 鏡文字を書く子は、上下左右の位置の識別が定かでない。 ● 文字を正しく書くには、始筆・終筆の位置や、途中の運筆が四角います目のどのあたりを通っているのか ということを正確に認知しないと正しく書けません。 位置を表す言葉を普段から、しばしば用いて慣れさせる。 |
|||||||||||||||
| (4) 5までの数は一瞬の間に見分けられる。10までの数の合成分解ができる。 | |||||||||||||||
| 特に、5までの数の合成(たしざん)・分解(ひきざん) 5は3と2 4と1 などの習熟は算数の学力の 最も基礎になるものです。 できれば10までの合成と分解が瞬時にわかるようにしてあげたいものです。 (10は0と10 1と9 8と2 ~ 10と0 9と1 2と8~) 0+10=10 1+9=10 2+8=10 3+7=10 ~ 10+0=10 9+1=10 8+2=10 7+3=10~ 10-0=10 10-1=9 10-2=8 10-3=7 10-4=6 10-5=5 10-6=4 10-7=3 10-8=2~ |
|||||||||||||||
| (5) 文字の読み書き 読み聞かせから 一人読みできる子に! | |||||||||||||||
| 読み聞かせから、できるだけ早い時期(5歳より4歳/4歳より3歳/~)一人読み出来るようにように なった子は学力の高い子に成長していきます。 |
|||||||||||||||
| 家庭学習の習慣は一生の宝物! | |||||||||||||||
| 家庭学習の習慣はひとりでにはつきません。 親子のチームワークで家庭学習の習慣をつけてあげましょう。 家庭学習の習慣は後になればなるほど大きな力を発揮します。 |
|||||||||||||||
| 家庭学習の習慣を身につけてもらった子はそれだけで大きな財産をもらったことと同じです。 家庭学習の習慣は親から子に贈る最高の贈り物になります。 |
|||||||||||||||
 日本学術研究社QRコード |
|||||||||||||||
ご注文のお客様 0120-706-702 ご質問のお客様 045-360-8858 Eメール : jls@gakujutsu.net URL : https://www.gakujutsu.net |
|||||||||||||||
| 幼児・園児教材 | 小学生教材 | 中学生教材 | 高校生・大学入試教材 | DVD・パソコン教材 | タブレット教材 | 学研の図鑑 | |||||||||||||||
| TOP | ショップ案内 | お支払方法 | お届け予定日 | 送料 | 販売システム | 特定商取引表示 | 個人情報保護 | よくあるご質問 | ご注文 | |||||||||||||||